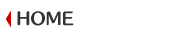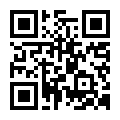活動日誌−活動日誌
【11.05.05】子どもの日
政治の責任が問われている
子どもの人権を重んじ、子どもの幸福をはかることを目的に設けられたのが「こどもの日」です。
日本社会を揺るがした大震災と原発災害は、日本の社会と政治が子どもたちの命と暮らしにどう向き合ってきたか、希望ある未来にむけた政治の責任をどう果たすのかを問うものとなりました。
東日本大震災と原発事故によっていまも12万人を超す住民が避難を余儀なくされています。1歳に満たない乳児をはじめ、子どもたちにとって2カ月近い避難所生活は限界担っているのではないのでしょうか。案じています。
津波に流され、崩壊した保育所は統廃合されずに、再建されるのでしょうか。学校が被災し、往復3時間かけた高校で学びが保障されるのでしょうか。合格した高校や大学の入学を辞退し、人生の進路を変えた生徒たちに希望を伝えることはできるでしょうか。
これまでも経済協力開発機構(OECD)加盟国のなかで、日本は子どものための社会支出が少ない国として指摘されてきました。とくに教育の無償化など、教育財政支出は最低です。ヨーロッパの多くは大学の学費が無償です。日本は高額の学費のうえに利子つき奨学金のため、多くの学生がアルバイトと卒業後の返還に苦しめられています。
乳幼児の保育・教育環境の整備も遅れています。保育所では非正規の保育士配置がすすめられてきました。保育所施設の最低基準を取り払い国や自治体の設置責任をなくす方向も検討されています。
真っ先に改善すべき耐震化率も、小・中学校で73・3%、保育所63%、児童養護施設では61・4%にとどまっています。一人親家庭の困難や「子どもの貧困」も大きな社会問題となってきました。
国連子どもの権利条約が義務付けた、子どもに「最善の利益」を与えるために政治の姿勢の転換がどうしても必要です。
昨年6月に国連子どもの権利委員会は日本政府に対し、日本が子どもの福祉サービスや政策策定過程に子どもの意見が考慮されていないことへの懸念を表明しています。
「子どもを権利を持った人間として尊重しない伝統的な見方が、子どもの意見に対する考慮を著しく制約している」と述べています。
家庭や学校、地域や社会のあらゆる場で、子どもの意見を尊重する、子どもがのびのびと意見を述べる権利を促進する―こうしたとりくみは新しい日本社会のあり方につながるものとなるでしょう。
子どもたちが笑顔の輝く日を一日も早く取り戻したいというのは、みんなの思いではないのでしょうか。。
生まれた家庭や住む地域で福祉や教育の条件に格差があってはならないし、それを保障するのが政治の責任であり役割です。どの子も平等に幸せに生きられる希望ある社会に向けて私も、力をつくしていきたいと思います。