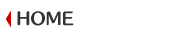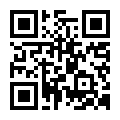市政の動き−議会報告
【10.11.29】11月臨時議会で質疑・反対討論
公務員の年齢差別削減は今までになかったこと
質疑11月臨時議会 質疑 2010年11月29日
日本共産党の石田正子です。
臨時議会に上程されました、『議案第76号 桑名市職員給与条例等の一部改正について』
日本共産党市議団を代表して質疑を行ないます。
日本経済の最大の問題はこの12年間、国民の賃金が下がり続けていることにあり、本当に円高、デフレを是正しようとしたら、家計を直接応援し、内需を活発にする政策への転換が必要です。
国民の賃金は、民間給与でいえば、1997年の平均467万円から2009年の406万円へと61万円も減少しています。正規雇用から非正規雇用への置き換え、リストラが横行し、これが、デフレを生み出し、円高という困難をつくっています。政府は、賃金を引き上げるワンパッケージの政策を打ち出すなど、政治がいま力を発揮すべきです。
大企業にため込まれた内部留保を設備投資や雇用に循環させていく経済構造の転換が必要です。そのためには内需を活発にすることが必要であり、その方策として人間らしい雇用を保障するルールづくりや、社会保障を充実させて将来不安を取り除く政策を求めるものです。
人事院勧告が2年連続のマイナス勧告となりました。これは人事院が比較方法や水準決定で機械的な民間賃金水準に固執しているためです。今年の「ベースダウンを実施した事業所は、1.1%程度に過ぎず、民間労使が賃金水準維持に努力したことは明白です。このような労使関係への配慮をみじんも示さず、機械的な「民間準拠」優先する姿には厳しく追及されるべきものです。当初人事院は、マイナス勧告の全額を56歳以上の職員全体に負担させようとしましたが、多くの反発があり、人事院は一部修正を迫られたとのことですが、結果として対象が限定され、当初やらないとしていた俸給表改定も行なうことになりました。しかしながら、この措置の対象者は俸給月額・俸給の特別調整額が1.5%減額され(俸給自体も減額されるうえに)その不当性は全く変わらないのです。今回の年齢による賃金削減は過去に例のないことです。
職務を変えずに賃金切り下げすることは職務給の原則に反するものではないのでしょうか。ここの職員が受けている号俸はこれまでの経験による能力の高まりやこれまでの成績が反映しているのではないのでしょうか。一定年齢に達したことのみを理由に賃金を切り下げることは「能力・実績主義」にも反するもので年齢差別に当たります。
そこで、今回2年連続のマイナス勧告と言うことですが、民間との較差(比較した差)を問題にしていますが、
(1)人事院のいう民間との較差とは
人事院の言う民間との較差についてお聞きします。
・民間とどれだけの較差があるとみているのですか。
・次の項目でもお聞きしますが、
若年層にはさほどの較差はないとみていることでしょうか。以前は公務員の安月給と言われたものですが、民間労働者には、歯止めない雇用不安あり、雇用が大きく崩される中、ワーキングプアの問題もあります。経済対策としても給与引き下げは景気の回復にも逆効果だと言われているのに較差だけが強調されるのでしょうか。まず1点お聞きします。
2点目として、
(2)今回の人事院勧告の特徴について
①若年層
②中堅層
③55歳以上
今回の勧告の中での特徴・問題点として
55歳を超える職員に対する一律の定率減額は、生活実態や生計費原則を無視した「年齢差別」とも いうべき賃金削減にならないのかそれぞれの年齢層でお聞きします。
(3)不利益遡及の考え方について(本年4月からの対象)
削減の対象は4月にさかのぼるのではないのですか。これは不利益遡及に値しないのでしょうか。
不利益になることはさかのぼらないという原則は貫かれないのでしょうか。
「人事院は代償機関の役割果たせ」と組合声明
8月11日付の市職労ニュースが庁舎地下組合事務所前に掲示されています。「・・・略私たち公務員の給料が世論に左右されることなく公務員が労働基本権を制約されその代償として機能すべき人事院であるにもかかわらず、我々の要求に耳を傾けることなく自らの主張を繰り返すばかりで官民比較の公表を拒み続けただけでなく、世論形成ともとれる情報管理の在り方などこれまでの対応は極めて遺憾であり人事院が自らの役割を放棄していると言わざるを得ません。・・・略・・・」とあります。
道理ない賃下げに反対
臨時議会反対討論 2010年11月29日
『議案第76号 桑名市職員給与条例等の一部改正について』日本共産党市議団を代表して反対討論を行ないます。
円高・デフレで、国民生活は苦しめられています。国民生活が悪化の一途
をたどっています。労働者は、年間一人当たり24万円合計8兆円起こすと言われています。働く人々の給料が減り、中小業者においては単価切り下げなどがおこなわれており、一方大企業においては11兆円の内部留保、52兆円のカネ余りがあり、日本経済に還流させる対策が取られておらず、内需の6割を占める家計を温める施策が一考に取られていません。このような状況下で人事院勧告は2年連続でマイナス勧告を出しました。
菅内閣は11月1日、2010年度の給与改定について、2010・人事院勧告どおりの実施を閣議決定しました。
官民較差「△0.19%、△757円」にもとづき、若年層を除く中高齢層の月例給の平均0.1%の引き下げ、55歳を超える行政職6級相当以上の職員給与の一律1.5%の減額、一時金の0.2月引き下げなどを内容とするもので、平均年間給与は9万4千円減の大幅な賃金削減となるもので、1998年から12年間で70万9千円の引き下げ、一時金にいたっては、1963年水準にまでさかのぼる水準となるということです。
勧告どおりの閣議決定は、職場からの切実な生活改善の声に全く耳を傾けていません。
「賃上げでこそ景気回復」にも逆行するものであります。
とりわけ、55歳を超える職員に対する一律の定率減額は、生活実態や生計費原則を無視した「年齢差別」ともいうべき賃金削減であり、道理なき賃下げへの職場からの怒りの声に背をむけた閣議決定の強行ともいうべきことです。
公務労働者の賃金の引き下げは、この間の地域最賃の大幅引き上げを求める全国の運動や、公契約条例制定の取り組みが進むなどの賃金改善の動きに逆流するものであり、公務関連労働者への影響とともに、内需拡大と生活危機打開を切実に求める国民の賃上げ要求と地域経済の建て直しにマイナス影響を及ぼすものであり、断じて認められないことです。
よってこの勧告に基づいての市職員の給与を引き下げることとする議案第76号 「桑名市職員給与条例等の一部改正について」は2年連続マイナス勧告を受けて年齢による差別的な扱いがあること、生活給を減額することついて問題を指摘して反対討論とします。